親の運転が心配になったら
「親の免許返納、いつ伝えればいいの?」私達世代の多くが、一度は心をざわつかせる問いではないでしょうか。
免許返納の手続き自体はとても簡単なようですが、なかなか親に言い出すことができません。
事故のニュースを目にするたびに「うちの親は大丈夫?」と不安になる一方で、運転は親にとって自立の象徴でもあり、簡単に手放せるものではないからです。
データで見る高齢ドライバーの現実
ちなみに日本経済新聞によると、75歳以上の免許保有者が年々増える一方、返納件数は4年連続で減少。高齢者の運転免許証の自主返納が伸び悩んでいるとのこと。
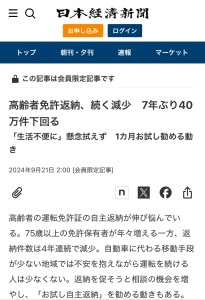
出典:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO83609850Q4A920C2CM0000/
つまり「まだ運転できるから返納は早い」と迷う高齢者は多いのです。これは、私の91歳の父の姿にも重なりました。
私の体験──“鍵を預かる”という第一歩
私が父と向き合ったのは、免許返納そのものではなく、「車の鍵を預かる」というファーストステップからです。
きっかけはこのお盆休みに、父がマイナンバーカードと介護保険証を相次いで紛失したこと。
結局は自宅で見つかりましたが、もし運転中にトラブルに遭ったら、とても一人では対応できないと判断したのです。
ただ、鍵を預かるのは容易ではありませんでした。父は頑なにこう言いました。
「一度取られたら、もう戻ってこない。そんなことをされるなら、生きている価値がない。」
この一言を聞いて、私は焦らず、命令することを避けました。そしてあえてこう伝えてみました。
「じゃあ、私が助手席に乗った時に運転してみて。1週間後にまた来るから、その時まで鍵は預かっておくからね。」
そう伝えると、父はようやく鍵を渡してくれたのでした。

不安を小さく解消する工夫
ただ鍵を預かるだけでは、父の不安は消えません。そこで次のようなルールも一緒に考えました。
• 週1回は必ず実家に行き、買い物や病院に付き添う
• 必要な用事を紙に書き出す
(ゴミ出し、孫や民生委員への手紙、季刊誌の振込、目薬の購入など)
• できることを周囲で分担する
(手紙やゴミは、生協の訪問時にお義姉さんにも手伝ってもらう)
• 急な用事は朝7時半までか夕方5時以降に電話で知らせる
こうして父は、「じゃあ、このゴミ出しは頼んでいいか?」と周りに任せることを覚え、一つひとつ不安を小さく解消し、鍵を渡してくれたのでした。
人間関係すべてに通じる“慌てない向き合い方”
親の免許返納は、すぐに答えが出る問題ではありません。でも、鍵を預かることから始めるなど、小さなステップで親の安全を守る道はあります。
この経験を通して私が学んだのは、慌てないこと・相手のリズムに合わせること・不安を小さく分解して一歩ずつ進むこと。きっとこれは、誰と向き合う時にも大切なことかもしれませんね。
免許返納まではまだ時間がかかりそうですが、『慌てず、寄り添い、ステップを踏む』ことを意識しながら、これからも父と向き合っていこうと思います。
今回は、【親の免許返納、いつ伝える?】50代に必要な“慌てない向き合い方”でした。毎日リセット!











